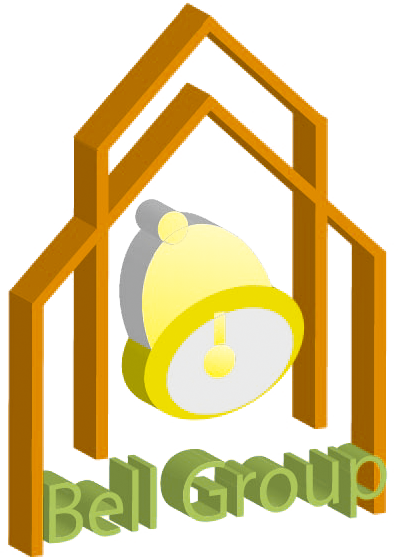コンクリート保護
わたしたちのできること
コンクリートを保護するってどういうこと?
硬くて頑丈なコンクリート。
でも、周りを見てみると「橋」「ダム」「建物」など、劣化したコンクリート構造物をたくさん目にすることがあります。
その理由は、コンクリートには自然界に大敵がいるからです。
その正体は「水(雨水)」。
流れる水がかかり続けると、コンクリート内に含まれるカルシウム分が溶け出てしまったり、表面を削ってしまうからです。
また水は「塩化物(海水や凍結防止剤など)」と混ざり合うことで、肉眼では確認できない微細なひび割れを通って、コンクリートの劣化因子をその躯体内に運び込んでしまいます。
コンクリートの劣化の8割以上が「水かかり」と言っても過言ではないでしょう。
つまり、コンクリートの保護というのは、
「水がもたらす被害からコンクリートを守ること」
いくら劣化部分、欠損部分を補修しても、元凶からコンクリートを守らなくては「無駄な補修」となってしまいます。
-

保護をしていなかったため、雪解け水と一緒に凍結防止剤が流れてきて「塩害」をおこしてしまった症例。
-

上部に溜まった水が溢れ、壁面に流れてきたことによって、コンクリートの表面が削れてしまった症例。
-

用水路内の壁面。使用期間中、水が水路内を流れ続けた結果、水が当たっていた部分の表面をボロボロにしてしまった症例。
長期的な保護を可能とするために「透気透湿性」のある材料を選定しよう
「透気透湿性」とは、水蒸気が通す性能のこと。
コンクリートは硬く密集しているように見えますが、全体の体積の約18%が、目には見えない微細な空隙(空洞や、空洞と空洞を繋ぐ道)、つまりスキマが空いています。
「アリの巣」を想像するとわかりやすいと思います。
地上に出るためのアリの通り道や、土の中にはアリの巣が、迷路のようになっています。
実際はもっと小さなサイズ(ナノサイズ)ですが、コンクリートの中も同じような構造です。
つまり、片側だけ水の対策を万全にしても、反対側からくる水(気温上昇により水蒸気となった水分)出ることができなければ、コンクリート内に必要以上の水を留めてしまうことになります。
コンクリートを保護する材料に「透気透湿性」がなければ、水や水蒸気は気温の変化で膨張・収縮を繰り返し、内側からコンクリートを壊していくことになります。
もし雪が降るような季節であれば、溜まってしまった水分は凍結融解(気温の変化で水が凍ったり解けたりを繰り返す現象)をおこします。
-

保護をしていなかったため、雪解け水と一緒に凍結防止剤が流れてきて「塩害」をおこしてしまった症例。
-

水蒸気が通ることができないと、塗装を押し上げてぷっくり膨れてしまうことに。
-

建物の外壁だって同じです。水蒸気が通れないと、押し上げられた外壁材ごと剥がれ落ちることになります。
コンクリート保護のポイント

-
01
透気透湿性を確保する
内部に滞留した水分・水蒸気の拡散経路を確保し、膨れ・剥離や凍結膨張圧を抑制。表層含水率を適正化し再劣化サイクルを遅延させます。
-
02
液相水を侵入させない
低吸水性・撥水性層で雨水・飛沫・融雪水の浸入経路を遮断し、塩分や溶脱のキャリアとなる自由水の供給を低減します。
-
03
劣化因子 (塩化物・CO₂ 等) を遮断
選択透過型の表面保護で塩化物イオン・二酸化炭素・硫酸イオンなどの拡散・吸着を抑え、鉄筋腐食・中性化・化学的侵食の進行を抑制します。
鈴木にはあります。そんな都合のいい「材料・工法」が!!
パーミエイトHS-300 含浸被覆工法
“含浸”で内部から吸水を抑制し “被覆”で外部劣化因子を遮断。さらに呼吸性を確保した多機能ハイブリッド保護システム。

橋梁(橋台・桁・地覆)・農業用水路・耐久性が求められる水回り構造物など、塩害 / 凍結融解 / 摩耗 / 中性化 が複合する環境で長期性能を発揮する“呼吸型”表面保護システムです。
中性化抑制率
100%
塩化物浸透抑制
100%
高透気透湿性
90〜99%
長期防食性
向上
※ 数値は供試体の参考値であり、実際の構造条件により変動します。
“含浸 × 被覆 × 呼吸性” の三位一体
含浸層
深部まで浸透し毛細管吸水と表層濡れを低減。内部含水率を安定させ凍害リスクを抑制。
被覆層
CO₂ / 塩化物イオン / 汚染物質の拡散を抑え、腐食・中性化・美観劣化を遅延。
呼吸性
水蒸気拡散を許容し内部膨れ圧を逃がすことで剥離・白華・膨れを防止。
3 要素のバランスにより 再劣化サイクル延長 / LCC 低減 をサポート。
従来含浸材との違い
従来シラン系
細孔内壁を疎水化し吸水は抑制するが、CO₂・塩化物イオン拡散は残存。製品によっては水自体の侵入抑制も限定的。

パーミエイトHS-300
無機系ポリマーが微細孔を選択充填し液相水 / 溶解塩を遮断。水蒸気拡散性を維持しつつ CO₂ 侵入を低減 → 中性化・ASR リスク抑制。

※ 概念図は模式表現です。実際の細孔構造・界面は条件により異なります。
主な特徴
- ●無機系ハイブリッドで紫外線劣化抑制
- ●“根付き”密着で高付着・剥離しにくい
- ●液相水 / 塩分 / CO₂ の侵入経路遮断
- ●高透気透湿性で膨れ・凍害リスク低減
- ●クリア / 着色(無機顔料で色褪せ抑制)
- ●補修部追従性を考慮した柔剛バランス
高透気透湿性 (90〜99%*) により内部に水分を閉じ込めず、凍結融解・膨れ・白華・剥離リスクを抑制し長期防食性を支援。
* 試験条件による範囲。設計採用時は現場条件での確認が必要です。

パーミエイトHS-300「着色」は建築でも活躍してます
一般的な有機塗料は、透気透湿性の性能が5~10%と言われています。水蒸気を外に逃がす効果が少なく、塗装に膨れがでたり、膨れが破けて剥がれることも少なくありません。
パーミエイトは無機塗料、加えて透気透湿性が90%以上なので、膨れや剥がれの心配はほぼありません。
しかも着色タイプは、日塗工の色合いを再現(色によっては近似色)することができ、むき出しコンクリートで完成では心配な環境での塗装に適しています。