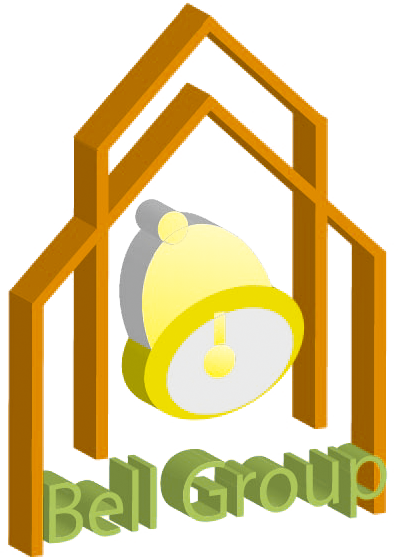防水工事
わたしたちのできること
その油断が雨漏りの原因に繋がります
こんな症状があれば、危険信号!
-

廊下や壁にひび割れがある
ひび割れたコンクリートが自然となおることはありません。今は小さなひび割れでも、水が入り込むことでコンクリートを固めているカルシウムが抜け出し、構造物の劣化とともに雨漏りに繋がることになります。
-

外壁の汚れが目立つ
水はコンクリートの天敵です。水たまりを放置しておくと、毛細血管のような細かいひび割れから水と一緒に劣化因子が入り込んでしまいます。その結果、建物の劣化から雨漏り繋がることもあります。
-

床隅や排水溝周りに水が溜まっている
水はコンクリートの天敵です。水たまりを放置しておくと、毛細血管のような細かいひび割れから水と一緒に劣化因子が入り込んでしまいます。その結果、建物の劣化から雨漏り繋がることもあります。
防水工事の耐用年数は一般的に8年~10年と言われています。
ですが、耐用年数内であったとしても、
天災や天候などの影響で防水効果が低下してしまうこともあります。
「小さな症状だから大丈夫」とひび割れや黒ずみを放置せず、業者の方に相談しましょう。
今なら簡単に補修できるものも、放置し劣化が酷くなれば
大きな修理費用に加え建物そのものの価値まで下がってしまうことになります。
その防水工事、鈴木にお任せください!
新設、既設問わず、防水工事が可能です!!
-

工場・倉庫
- 屋上
- 床
- 壁
- 地下ピット
-
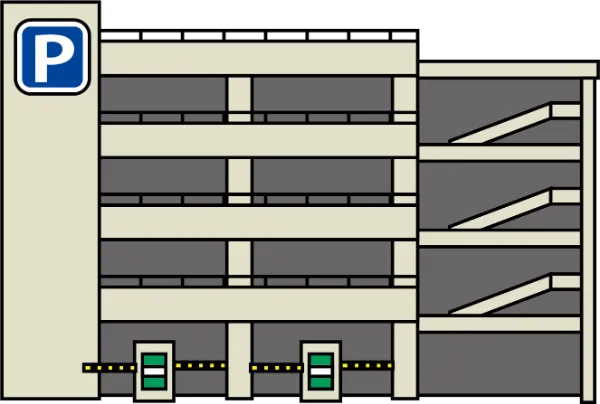
自走式立体駐車場
- 屋上
- 走行通路
- スロープ床
-

商業施設 / 空港 / 病院
- 屋上
- 外壁
- 床
- 駐車場
- 地下ピット
-

マンション・アパート
- 屋上
- 共用廊下
- 玄関
- 階段
- バルコニー
注:既存の防水材が塗布されている場合は、撤去が必要になることがあります。
鈴木の防水工法
鈴木では 「コンクリート自体を防水層化する工法」 と 「異素材取り合い部の漏水リスクを封じる工法」 を組み合わせ、構造特性と劣化要因を踏まえた最適なプランを提案します。
コンクリート緻密化 防水改質
けい酸塩系材料を散布し内部で化学反応を起こし微細空隙を充填。構造体そのものを「防水層」に改質し再発リスクを低減。
- ■打設直後〜早期段階にも適用可
- ■劣化因子(塩化物・CO₂・水)侵入抑制
- ■新規ひび割れ発生時も未反応成分が追従反応
異素材取り合い部 接合防水
収縮率の異なる部材(排水ドレン・塩ビ管・鋳鉄管 等)周辺の継ぎ目を高追従かつ密着性の高い特殊材で一体化し漏水経路を遮断。
- ■従来シーリングより剥離リスク低減
- ■微細な動き・熱伸縮に柔軟追従
- ■ガラス/ポリカ以外幅広い基材に対応
METHOD 01|コンクリートを緻密化し水密性を高める
液体材料を散布 ⇒ 内部の水酸化カルシウムと反応し生成物が毛細管空隙を充填。これにより含水率低下・中性化進行抑制・水分移動阻害を同時に達成します。
仕組み
反応生成物が毛細管径を縮小し水分移動抵抗を増加。未反応成分は後発ひび割れ発生時に再反応し自己追従的に空隙を充填。
主な効果
- ・長期的な防水性
- ・中性化/塩害因子の侵入抑制
- ・ひび割れ幅進展抑止
- ・凍害/膨潤リスク低減
適用部位
- ・打設初期スラブ
- ・屋上/駐車場スラブ
- ・地下ピット/壁
- ・雨掛かり頻度の高い水平面
反応生成物がコンクリート内部の毛細管空隙を塞ぎ、構造体そのものを防水層化。
未反応成分が残存するため、新たな微細ひび割れ発生時も雨水を媒介に再反応し、長期的なセルフシール性能を発揮します。
防水工事例
脱型直後にけい酸塩系防水材を散布し、硬化過程での水分蒸発と乾燥収縮による微細ひび割れ進展を抑制。


METHOD 02|異素材取り合い部を高追従接合
収縮率や熱膨張が異なる部材境界は応力集中が起こりやすく、従来のコーキングでは界面剥離 → 水の侵入 → 劣化促進サイクルを招きます。高機能材料で柔軟接合し漏水経路そのものを断ちます。
課題
部材ごとの伸縮差で界面にせん断応力 → シーリング亀裂・剥離が発生し毛細浸入路を形成。
解決
- ・高追従/弾性/密着性
- ・界面剥離抑止
- ・長期防水保持
適用例
- ・排水ドレン周り
- ・塩ビ/鋳鉄管立上り
- ・入隅/出隅部
- ・金物貫通部
材料自体の柔軟性と密着力で微小な動きにも追従し界面剥離を防止。
従来工法の「打ち替え頻度」を低減し、ライフサイクルコストを抑えます。
取り合い部 施工例
排水ドレン・入隅部を高追従材料で接合し浸入経路を遮断。従来シーリングで頻出した界面剥離を抑制。